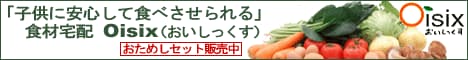ユダヤ人の頭のなか [book]
ユダヤ人の頭のなか / アンドリュー・J・サター (著), 中村 起子 (翻訳)
あとで書く。
株・FX・投信・副業のための確定申告の書き方 平成21年3月16日締切分 [book]
株・FX・投信・副業のための確定申告の書き方 平成21年3月16日締切分 / 中経出版確定申告プロジェクト (著), 落合 孝裕
確定申告ガイド本はいろいろ出ていますが、本書は住宅購入やアフィリエイトの副収入などは省き、主に株、FX、投信といった投資関係に特化しています。
そのため、他の確定申告本が「広く浅く」であるのとは異なって、投資分野での確定申告について「狭く深く」解説してあります。
税制の説明からさまざまなケースの申告書の具体的な書き方例まで、税金の話は難しいのですが、じっくり読むとよくわかります。
個人的には、特定口座と一般口座の違い、外国税額控除を受けると不利になることもある、などを知ることができ、とてもためになりました。
最近一般的になってきた ETF, FX, REIT や外貨 MMF, 海外ETF, 外国債券などの解説もあり、おすすめです。
あと、この本を読んで知ったのですが、中経出版はネット書籍サービスというウェブサービスを行っていて、購入した書籍をネット上で読むことができます。
Google ブックや Amazon なか見!検索よりも使いやすく便利です。
以下、読書メモ。
p.8
* 税金を納める申告の場合 => 2009年 (平成21年) 2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)まで
* 税金を返してもらう申告 (還付申告) の場合 => 2009年 (平成21年) 2月16日の前でも提出可能 (1月1日以降)申告のために必要な書類が手に入る時期…取っておくようにしましょう
* 2008年 (平成20年) の年末ごろ => 給与所得者の源泉徴収票 … 給与所得の申告に必要
* 2008年 (平成20年) の取引の都度 => 株式の「取引報告書」 … 「一般口座」の申告に必要
* 2009年 (平成21年) の1月末まで => 特定口座年間取引報告書 … 「特定口座」の申告に必要
* 2009年 (平成21年) の1月ごろ => 公的年金等の源泉徴収票 … 年金収入者の申告に必要
* 2009年 (平成21年) の1月中旬ごろ => 申告用紙 … 税務署に備えつけられる
p.31
* 譲渡所得グループ (分離課税) このグループ内で損益通算が可能 => 損益通算をしても損失が引ききれずに残った場合には3年間の繰越控除ができます (未上場株式を除く)
* 上場株式
* 信用取引
* 上場外国株式
* 株式投資信託 (買取りの場合)
* ETF (上場株式投資信託)
* REIT (上場不動産投資信託)
* 未上場株式
* 雑所得グループ (分離課税) このグループ内で損益通算が可能 => 損益通算をしても損失が引ききれずに残った場合には3年間の繰越控除ができます
* FX取引 (くりっく365)
* 日経225mini (日経平均先物)
* 商品先物取引
* オプション取引
* 雑所得グループ (総合課税) このグループ内で損益通算が可能 … 3年間の繰越控除は認められていません
* FX取引 (くりっく365 以外の相対取引)
* 金・プラチナの定期積立による所得 (ケースによる)
* 外貨預金の為替差益 (差損については他の所得との損益通算はできません)
* 年金収入による所得
* 原稿料・講演料収入などによる所得 など
* 譲渡所得グループ (総合課税) このグループ内で損益通算が可能 … 3年間の繰越控除は認められていません
* 金・プラチナの売却による損失
* 給与所得
* 配当所得
* 不動産所得
* 事業所得
* 一時所得
* 雑所得
p.56
一般口座
メリット
* 「みなし所得費の特例」が使える
* 売却益から税金が引かれないので、その分を再投資に回せる
* 売却益が 20万円以下 (正確な条件は本文参照) のサラリーマンは申告不要
デメリット
* 譲渡所得の計算が必要 (面倒)
特定口座 (源泉徴収なし)
メリット
* 申告が簡単 (譲渡所得の計算不要)
* 売却益から税金が引かれないので、その分を再投資に回せる
* 売却益が 20万円以下 (正確な条件は本文参照) のサラリーマンは申告不要
デメリット
* 「みなし所得費の特例」が使えない
特定口座 (源泉徴収あり)
メリット
* 申告が不要
* 申告が不要なため、株式の売却益による譲渡所得が合計所得に加算されない→扶養控除・配偶者控除などの対象者からはずれずにすむ
デメリット
* 「みなし所得費の特例」が使えない
p.122
外国株式の配当や海外 ETF の収益分配金は、外国で配当収入から外国所得税を天引き (たとえばドルベースで) されたあと、その残高について国内で源泉徴収 (円ベースで) されることになっています。つまり、外国と日本の双方で税金が課税される形です。
外国の源泉徴収税率は国により異なりますが、租税条約を締結している場所は、通常、その条約に定める制限税率の範囲内で税金が天引きされます (源泉徴収税率は 15% の国が多い)。日米間では 10%、中国の場合には、中国国内では課税されません。
外国株式の配当や海外 ETF の収益分配金を申告する場合、「配当控除」を適用することはできません。そのかわり、外国で源泉徴収された税金については、「外国税額控除」を受けて全部または一部を取り戻せる可能性があります。
ただし、配当所得は総合課税の対象であるため、「外国税額控除」を受けようとして申告をすると、かえって納税額が増える可能性があります。たとえば、アメリカ株式の配当金は源泉徴収税率が 10% であるため、課税総所得が 195万円超の人は申告をすると不利になります。気をつけましょう。
2008 年 11 月に読んだ本 [book]
今月は 5 冊読みました。

ref.[2008-11-25-1]

ref.[2008-11-21-1]
最後の授業 ぼくの命があるうちに DVD付き版 / ランディ パウシュ (著), ジェフリー ザスロー (著), 矢羽野 薫 (翻訳)

ref.[2008-11-19-1]
ETF投資入門 上場投信・徹底活用ガイド / 太田 創 (著)

ref.[2008-11-13-1]
キャリアをつくる9つの習慣 これが価値を生み出す最新の働き方だ / 高橋 俊介 (著)

ref.[2008-11-10-1]
「残業ゼロ」の仕事力 [book]
仕事を効率化し、残業をなくすキーはデッドラインの設定です。
多少強引なやり方でも、信念を持って残業を禁止し、限られた勤務時間の中でデッドラインが決められた仕事を片付けるよう社員を追い込むことで効率を上げるというヘビーな内容です。
この方法をコピーして同じように行うというのはかなり難しいと思います。
しかし、その内容には参考にできる点が多々あると思います。
その他、フォロワーシップや TTP(徹底的にパクる)といった考え方の Tips や、1 案件を 2 分でこなす早朝会議の内容についても書かれています。
「残業ゼロ」とはいかないまでも、仕事を効率化するうえで、非常に参考になる内容です。
以下、読書メモ。
p.26
それでは、どうすれば残業をなくすことができるのでしょうか。
細かい部分はあとからお話しますが、まずは、仕事のデッドラインを決め、それを社内で徹底させることからはじめます。
pp.28-29
以前、ある女性経営者から、「吉越さんの公演を聞いて『ノー残業デー』を導入しようとしたら、仕事が回らないからやめてくれ、という反対の声が日に日に高まってどうにもならなくなってしまった、どうしたらいいのでしょう」というメールをいただきました。それに対する私の返事はこうです。
「社長が『ノー残業デー』を導入するといったら導入するのです。以上、終わり」
そんなもの、時間がきたら有無をいわさず、オフィスの電気を消してしまえばいいじゃないですか。さらに、違反した社員や部署には罰金を課す。残業が発覚するたびに反省会を開き、なぜ就業時間内で終わらなかったのか、誰が聞いても納得する答えが見つかるまで追及の手を緩めない。
社員の誰もが、「こんな思いをするくらいなら残業なんてしないほうがマシだ」という気持ちになれば、自然と残業はなくなります。
p.45
天才ではない私は、どうやって問題に立ち向かえばいいのでしょう。そう、大きな問題を分けて小さくするのです。大きすぎてどこから手をつけたらいいかわからない問題に遭遇したら、まずは絡んでいる鎖をほどくところから始めてください。そして、どんどん小さい問題に細分化していく。そうしているうちに、「これなら自分でもなんとかできる」というサイズになります。そうしたら、それらを一つひとつ解決していきます。
p.51
本当に仕事の効率を上げたいのなら、厳しいデッドラインつきの仕事を、これでもかというくらい押し込めばいいんです。それで、一分一秒も惜しいという状況に追い込まれれば、自然と仕事の処理速度が速くなる。こうやって、早く仕事ができる人間になるほうが、優先順位をああだこうだと考えるより、よっぽど確実に仕事をこなせると思っています。
p.54
デッドラインを決める際、気をつけなければならないのは、相手の顔色を見て、「これくらいならできるだろう」という配慮をしないことです。そうではなく、あくまで「会社に取って正しいことを優先する」、これがデッドラインの決め方の極意です。
p.72
私のいう「完璧なたたき台」とは、現状はどうなっているのか、何が問題なのか、どう対処すべきなのか、それにはどれくらいの時間や費用がかかるのか……、そういうことを担当者が会議に先立ち整理して解決策をまとめてくる、ということです。
pp.72-73
結論は担当者がたたき台として用意してくる。会議はそれをいいかどうか判断するだけの場なのです。
p.73
では、情報が足りなかったり、質問に対して担当者が理路整然と答えることができなかったりしたらどうするか。それは課題に対する詰めがまだ甘い、ということですから、そんな状態で長々と議論をしても仕方ありません。そういう場合は足りない部分を指摘して、さらに「誰が」「なにを」「いつまでに」ということをみんなの前で明確にしたうえで、さっさと担当者に差し戻します。
p.81
そして、もう一つ大事なのが、会議を「デッドライン」を決める場にするということです。
p.96
自慢じゃありませんが、私はオリジナルに対するこだわりもなければ、他社の事例をまねることにもまったく抵抗がありません。真似だろうがなんだろうが、それが自分の会社にとって役に立つことなら、どんどん取り入れるべきなのです。ちなみに、私はこの考え方を「TTP(徹底的にパクる)」と名づけて、今でも仕事の信条の一つにしています。
p.112
大切なことは毎日の仕事を終えたあとの 3 時間あまりを、「自分の人生のために投資する」、と考えることです。
p.149
日本のホワイトカラーはポジションによって役割は一応規定されているものの、一人ひとりの仕事の範囲や責任はきわめて曖昧なのが現状です。だから、誰がどの作業の効率をどれだけ上げれば全体のスピードがこれだけ速くなる、といった具体的な計測がまったくできないのです。かといって、工場のように社員が整然と一つのラインに並んで仕事をするわけにもいきません。ここでも、威力を発揮するのはデッドラインです。仕事を個人単位に割り振り、デッドラインをつけて厳しく管理する。こうすると、誰がボトルネックになっているかは一目瞭然です。
サンクコスト時間術 [book]
サンクコスト時間術とは、S-TiBA(エスティーバ) のサイクルを回すこと。
S-TiBA(エスティーバ) とは、
1. Situation (状況判断)
2. Time Left (残り時間)
3. Best Answer (最善の答え)
4. Action (アクション)
つまり、過去の無駄になった投資はもったいがらずに忘れ、現在の状況を判断し、制限時間がある将来のために最前の答を探し、実行する、ということ。
まとめてしまうとこれだけなのですが、この考え方を頭に入れておいて、習慣化すると役に立ちそうです。
サッカーや麻雀の例えが多いので、それらに馴染みがない読者にはわかりにくいかもしれません。
p.20
今回のケースでは、このバス待ちで失った二〇分間がサンクコストになります。サンクコストとは管理会計や意思決定論で使われる考え方ですが、「もはやどうにもならないもの。よって、考えるうえで除外すべきもの」という意味です。
p.21
もはや手の届かない、海の底に沈んでしまったものにこだわっても、何も起こりません。であれば、それを「なかったこと」にして、物事を考えればよいのです。
最後の授業 ぼくの命があるうちに DVD付き版 [book]
最後の授業 ぼくの命があるうちに DVD付き版 / ランディ パウシュ (著), ジェフリー ザスロー (著), 矢羽野 薫 (翻訳)
あとで書く。
ETF投資入門 上場投信・徹底活用ガイド [book]
ETF投資入門 上場投信・徹底活用ガイド / 太田 創 (著)
タイトルに「入門」とあるように、とても基本的な内容になっています。
内容は、ETF と投資信託の違い、主要な ETF 銘柄の紹介、投資法 (ドルコスト平均法) など。
ETF をこれから始めようという人が対象です。
ただ、すでに投資信託などを運用している人には基礎的過ぎて退屈だと思います。
キャリアをつくる9つの習慣 これが価値を生み出す最新の働き方だ [book]
キャリアをつくる9つの習慣 これが価値を生み出す最新の働き方だ / 高橋 俊介 (著)
9つの習慣とは、下記です。
- 勝負能力
- 現場体験
- ネットワーク
- 仕事に意味付け
- 個人ブランディング
- 相手の価値観を理解する
- ポジティブに巻き込む
- 経験と気付きで学ぶ
- 仕事の言語化、仕事の見える化
はじめの 3 つは、見出しだけ読むと、習慣の説明なのに「 勝負能力」などと名詞になっていてイメージが湧きにくいかもしれません。
しかし、著者の言いたいことは最初の 5 つ、「勝負能力」、「現場体験」、「ネットワーク」、「仕事に意味付け」、「個人ブランディング」で、残りの 4 つは、それらの追加の説明といった印象を受けました。
説明は「こうすればよい」だけでなく、その後に「では、そうするにはどうすればよいか」と踏み込んだ説明がなされているのがよかったです。
ただそれでも、例があっさりているので、抽象的な印象が拭えません。
もう少し具体的な解説があるとよかったのかも。
以下、読書メモ。
p.16
勝負能力とは、これを発揮すればいざというときに高い成果を出すことができる、その人らしい能力のことをいう。好ましいキャリアを築いている人は、この勝負能力を活かした独自の「勝ちパターン」の持ち主だといえよう。それでは、数ある人間の能力のうち、どういうものが勝負能力になり得るのか。条件をひとつ挙げれば「楽しく発揮できる能力」になる。自然体で使うことができて、しかも使うときに苦痛を感じないというのが、勝負能力というわけだ。
楽しく発揮できるということがなぜ大事か。楽しく発揮できない能力を、無理やり鼓舞して勝負に使った場合、長い間にいずれは燃え尽きてしまう可能性がきわめて高いからだ。
p.32
いくら経営学の MBA をもっていようが、現場経験もない人間が会社経営などできるはずがないという言い方は、ある意味正しい。現場に行かなければみえない問題点や課題はたしかにある。しかし、ただ闇雲に現場を歩きまわったところで、肝心なものは何もみえないだろう。重要なのは、あらかじめ仮説や問題意識をもって現場に行くということ。それで「あれはこういうことだったのか」と腑に落ちたとき、本当の気づきや発見が生まれるのだ。さらに、それを自分の言葉で概念化していけば、生きた知識として自分の中に蓄積されていく。
pp.41-42
信頼のおける人たちとネットワークを築き、そこにある人間関係に投資しなさい。そうすればいずれあなたにもメリットがありますよ――。社会関係資本とはこういうことをいっているのである。ということは、組織内での差別化やキャリア形成にいい影響を及ぼす社会関係資本を築くには、周囲に信頼されるような行動をとることと、人間関係に継続的に投資し続けることの二つを習慣化すればいいということがおわかりだろうか。私はこれを「布石」と、「投資」の習慣化と呼んでいる。
ところが、実際はそれだけではない。もうひとつ忘れてはならない重要なことがある。それは、出会った人間が信頼に足るかどうかを見抜くということ。社会関係資本をうまく活用している人というのは、例外なくこの「見抜く能力」に長けているといっていい。見抜く能力を身につけるには、さまざまな人とフェイス・トゥー・フェイスのコミュニケーションを重ねていくのがいちばんだ。
p.50
仕事と趣味ではどこが違うのか。それは、価値を創造し提供しているかどうかという点だ。
p.51
自分の仕事の意味を知るには、まず、自分の顧客は誰なのかを明確にし、次に、その顧客にどんな価値を提供しているのかを確認するといい。
p.60
「私はこういう価値を提供している」ということを自覚し、それを踏まえた行動をとり続けることで周囲に証明し、認めてもらうというのが個人ブランディングなのだ。
p.63
できればブランドは一つではなく、二つか三つあったほうがいい。そして、それらを自分で意識してやり続けるのだ。同時に、自分にはこういう特徴があるということを、口に出して積極的に周囲にアピールする。とくに、影響力の強いキーパーソンには、ことあるごとに言葉と態度でそれを示しておく。いわゆる個人ブランディングの布石行動だ。
2008 年 10 月に読んだ本 [book]
今月は 1 冊読みました。
* 時間のプロが教える これでラクになる!「キッチン時短術」 / あらかわ 菜美 (著)

ref.[2008-10-20-1]
時間のプロが教える これでラクになる!「キッチン時短術」 [book]
時間のプロが教える これでラクになる!「キッチン時短術」 / あらかわ 菜美 (著)
キッチンにまつわる時短術が書かれています。
鍋の再利用など、「魚柄 仁之助さんのひと月9000円の快適食生活」と共通するワザもあります。
自分が使いやすいワザから生活に取り入れていくとよいと思います
以下、読書メモ。
p.36
6 「とりあえずの一品」で、時間を稼ごう夏の時期は枝豆を欠かしたことがありません。枝豆のない時ももちろんあるので、手をかけないでパッと出せるものを用意します。ちくわときゅうりもいいし、キャベツの葉っぱも時間稼ぎの一品になるのですよ。
p.39
7 毎日の料理に大活躍!三つの「お助け野菜」じゃがいも・にんじん・玉ねぎの三つを使ってできる料理をパッとあげただけでも、そう、誰でも知っているカレー、ホワイトシチュー、ビーフシチュー、ポトフ、ボルシチ、肉じゃが……。
pp.42-43
料理を作る時間がない時、帰りがけにお総菜売り場で買うのもいいでしょう。でも、たくさんの量を買わなくても、それに家にある野菜をプラスするだけで、手を加えたボリューム満点・栄養満点の一品になります。
pp.102-103
私は今でも、おにぎりをよく作ります。夕食の支度が間に合わない時、子どもにスナック菓子をつまみ食いさせないために。
p.127
私は買い物のやり方を変えました。「家にない食材」をメモするのではなく、「残り物」「家にあるもの」だけをメモして買い物に行くことにしたのです。
2008 年 9 月に読んだ本 [book]
今月は 5 冊読みました。
* 儲かる会社にすぐ変わる! 社長の時間の使い方 / 吉澤 大 (著)
ref.[2008-09-29-1]
ref.[2008-09-28-1]
ref.[2008-09-19-1]
* 気持ちよく生きるための「ちいさな実行」 / あらかわ 菜美 (著)
ref.[2008-09-12-1]
* 詳解 Objective-C 2.0 / 荻原 剛志 (著)
ref.[2008-09-09-1]
儲かる会社にすぐ変わる! 社長の時間の使い方 [book]
儲かる会社にすぐ変わる! 社長の時間の使い方 / 吉澤 大 (著)
あとで書く。
ひと月9000円の快適食生活 [book]
乾物や干物、根菜など昔から和食に取り入れられている食材をとることが薦められているあたりは、「粗食のすすめ」で有名な幕内秀夫さんと同じ考え方です。
本書は、プラス魚柄流段取り術、時間節約術が書かれています。
常識にとらわれない発想で、より楽により安くよりおいしく栄養が取れる小技が満載です。
各節は簡潔に書かれているので、興味の向くままに、好きなところから読むことができます。
世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント [book]
タイトルにもある通りわかりやすいプロジェクト・マネジメント本です。
PMP 試験対策というよりは、実戦で役立つ内容で、プロジェクト・マネジメントに必要なトピックが網羅的に簡潔にまとめてあります。
プロジェクト計画については研修を受けたことがありますが、その内容はほぼ全て網羅されているように思いました。
しかも、1章1章が短いので、読みやすいです。
あまり具体例が挙げられていないため、プロジェクト・マネジメント初心者にはピンとこない部分があるかもしれません。
しかし、いくつかプロジェクトを経験した方には共感できる部分、ためになる点が多くあります。
「PMBOK ガイド本 (プロジェクトマネジメント知識体系ガイド第3版)」 を読む前に、まずは本書を読んでみることをおすすめします。
気持ちよく生きるための「ちいさな実行」 [book]
気持ちよく生きるための「ちいさな実行」 / あらかわ 菜美 (著)
自分の部屋をもっと好きになって、ひとりの時間を楽しめるような工夫が書かれています。
例えば、
p.32
テーブルの上にものが何もないと、びっくりするほどお部屋がスッキリして広く見えます。
確かにテーブルの上はごちゃごちゃしやすいです。
そこをキレイに保つことで、部屋の他のごちゃごちゃしたところも片付けたくなります。
薄くて簡単に読めるので、一気に読んでしまって、自分のやる気を引き出すのに良いと思います。
波動やマイナスイオンといった、うさんくさい部分もありますが、そのへんはサクッと読み流して。
以下、読書メモ。
p.35
全部左側に寄せて置き、右側を少し空けます。右側に少しスペースが空いていると、ものを取り出したりする時に、右にずらせるので動作がスムーズになるのです。
p.67
いやなことがあったついでに、あえて他にもいやなことをします。
p.68
今日をムダにしなかった。その気持ちが、もっといい明日につなげようとプラスに蓄積されていくのです。
p.118
たったの5分でも続けると、頭がさぼらなくなるのです。
〜略〜
つまり、継続するということは、頭の中の電源が on 状態、ということなのです。
詳解 Objective-C 2.0 [book]
詳解 Objective-C 2.0 / 荻原 剛志 (著)
本書では、Objective-C を網羅的に学ぶことができます、たぶん。
(たぶんというのは、Objective-C を知っていた訳ではないので)
少なくとも、主要な部分は分かったような気がしました。
Objective-C は C++ や Java を経験していると、似ている部分も多く理解しやすいと思います。
また、キー値コーディングなど、スクリプト言語に似ている部分もあります。
ただ、メモリ管理については独特なものなので、熟読が必要でした。
あとは、Cocoa フレームワークに関する書籍を読んだり、サンプルプログラムを読んだり、動かしたりして、フレームワークの使い方に慣れて行けば、Mac OS X や iPhone のアプリを作れるようになると思います。
2008 年 8 月に読んだ本 [book]
今月は 5 冊読みました。
《続きを読む》
案本 「ユニーク」な「アイディア」の「提案」のための「脳内経験」 [book]
案本 「ユニーク」な「アイディア」の「提案」のための「脳内経験」 / 山本 高史 (著)
スコープは、サブタイトル通り、「ユニーク」な「アイディア」の「提案」のための「脳内経験」です。
あらゆる経験を効率よく積むための「脳内経験」でないことに注意。
《続きを読む》
うおつか流生活リストラ術 生き活き人生シンプルライフ [book]
うおつか流生活リストラ術 生き活き人生シンプルライフ / 魚柄 仁之助 (著)
読んでみて、著者はとても頭がいい人なんだ、と感じました。
問題の本質をとらえ、それを解決するためにはどうすればよいのかを考え、実践できる人です。
本書に登場するそれぞれのエピソードは生活に密着した tips のようですが、その裏にある著者の考え方を見習い、真似していきたいです。
p.220
私が公開したいのは、私がつくったニセ・ウイスキーのレシピでも、改造したコタツ兼特大テーブルのつくり方でもありません。どこに目をつけ、どんな発想で、あり余っている物、処分に困っている物を自分に役立つ物に買えたか?という点なのです。
以下、読書メモ。
《続きを読む》