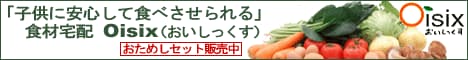頭のいい人が儲からない理由 [book]
著者の言う「頭のいい人」とは学校の勉強ができる人、もっと言うと学校の勉強しかできない人を指します。
「儲かる」とはビジネスの世界で生き残ることです。
つまり、自分の頭で考えないで解を図書館に求めるような人は成功しないということ。
では、勝ち残っていくにはどうしたら良いか。
p.16
ビジネスのメカニズムを理解し、なおかつそれを徹底して追求できる者だけが生き残るのである。
「徹底して追求する」とはどういうことか。
非常に単純化していうと、人が一努力するところを、自分は二努力するということだ。たとえば、戦略を考えるのに十の仮説を出したら、そこでやめず、さらにもう十捻り出す粘りがあるなら、その人のサバイバル能力はかなり高いといえよう。
さらに、
p.34
私の知っている世に成功者と呼ばれる起業家たちは例外なく、もうこれ以上無理だというくらいギリギリのところまで考えて考えて、頭の中に完璧なイメージをつくりあげてから行動を起こしている。まだ何も実現していないことを、あたかも見てきたかのごとく話せるくらいに。これが重要だ。
成功には努力や忍耐が必要というのは、他書でもよく述べられています。
一方、考えてから動くか、動きながら考えるかは、人によって違うのではないでしょうか。
第2章 「常識はビジネスの敵だ」は、「ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する 絶対に失敗しないビジネス経営哲学」(島田 紳助) [2008-03-20-1] と同じような内容です。
あと、技術志向のエンジニアが勘違いしそうなのが、優れた技術は受け入れられるに違いないという幻想。
営業というか、売り方、売るための戦略も重要です。
p.114
マーケットというのは、安ければ売れるとか、広告宣伝の量が多ければ人気が出るというような単純なものではないのである。
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計入門 [book]
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計入門 / 橘 玲 (著)
法人の税上の有利さはよく分かったのですが、会社を作ってもうまくいかないと、結局収入は減ってしまうので、難しいです。
以下、読書メモ。
《続きを読む》
2008 年 4 月に読んだ本 [book]
今月は 6 冊読みました。
《続きを読む》
チームハックス 仕事のパフォーマンスを3倍に上げる技術 [book]
チームハックス 仕事のパフォーマンスを3倍に上げる技術 / 大橋 悦夫 (著), 佐々木 正悟 (著)
p.14
本書で一番の要点となるハックは、スケジュール、作業記録、タスクリストという、仕事の進捗に関わる情報を、可能な限りメンバーと共有してしまうことにあります。
とあるように、本書の趣旨はスケジュールや作業記録を Wiki などで共有することにあります。
ただ、利点は頭では分かるのですが、導入障壁は高そうです。
本ハックを成功させるためにはチームメンバー全員が強制ではなく進んで各個人の予定や実績を公開しなければなりません。
「チームハックス」だけに一人でこっそり試してみるわけにもいかず、
p.258
メリットの享受に至るまでには、予定や実績、それにタスクリストを広範に開示してしまうことについて、抵抗感はありました。少なくとも私にはありました。この問題にはくどいほど本書で取り上げましたが、その理由は私と同じように感じる人が多くいるだろうと想像したからです。この問題を何らかの形で克服しないと、「チームハックス」は一歩も前に進みません。克服するためのハックスは、第 3 章にまとめています。
とありますが、第 3 章の内容では克服は難しいように感じました。
大人の投資入門 真剣に将来を考える人だけに教える「自力年金運用法」 [book]
大人の投資入門 真剣に将来を考える人だけに教える「自力年金運用法」 / 北村 慶 (著)
「ポートフォリオ」について入門書を読んで何となく知っていましたが、本書ではより 1 歩踏み込んでポートフォリオ運用について知ることができました。
個人的には、「ボラティリティ」という考え方を知ることができてよかったです。
最近は年金危機が叫ばれていますが、本書は、
p.56
本書でお薦めする『私的年金』は、公的年金を補完するもの、という位置づけです。つまり、公的年金と必要資金の差額である『年金ギャップ』を埋めるために、『私的年金』を作ろう、ということを本書で提案しているのです。
p.140
ここで、この『公的年金』のアセット・アロケーションを (A) とします。
さて、私たち普通の市民の年金は、『公的年金』 + 『私的年金』から成り立ちます。
そして、その合計のポートフォリオが理想の資産配分になっていることが望ましいわけです。
ここで、『私的年金』のアセット・アロケーションを (B) とし、年金全体のアセット・アロケーションを (C) とすると、以下のような等式が成り立ちます。(A)『公的年金』+ (B)『私的年金』 = (C)私たちの年金全体
という立場です。
しかし、公的年金を信用する/しないにかかわらず、各個人が自分の考えるアセット・アロケーションでポートフォリオ運用を行えるような内容となっています。
以下、読書メモ。
《続きを読む》
トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦〈1〉ブランド人になれ! (トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦 (1)) [book]
あとで書く。
沖縄やぎ地獄 [book]
あとで書く。
自助論 人生の師・人生の友・人生の書 [book]
自助論 人生の師・人生の友・人生の書 / サミュエル スマイルズ (著), Samuel Smiles (原著), 竹内 均 (翻訳)
勤勉さ、誠実さ、努力、それを継続することを求める厳しい言葉が続きます。
述べてある事柄は頭では分かっていながらなかなか実践できないものが多く、たるんでいるときに読み返すのが良さそうです。
以下、読書メモ。
《続きを読む》
2008 年 3 月に読んだ本 [book]
今月は 7 冊読みました。
《続きを読む》
沖縄上手な旅ごはん 美ら島に遊び、うま店で食べる [book]
沖縄上手な旅ごはん 美ら島に遊び、うま店で食べる / さとなお (著)
あとで書く。
頭のいい段取りの技術 [book]
第1章で「段取り」とはなにかを解説し、以降の章で「予定・時間管理」、「環境・情報整理」、「知的作業」、「コミュニケーション」について段取り術を詳解しています。
個人的に最も参考になったのは、第四章の「知的作業」段取り術。
p.108
まず冒頭に力を入れる
p.109
文章の読み手の脳が本能的に欲しがるこの大枠を文章の冒頭で与えることが重要なのです。
p.113
「企画書」は途中放棄されてもよい順番で書け
p.115
読み捨てられては困るものほど前に置いて、読み捨てられても被害が小さいものほど、後ろに置くということです。
p.122
会議終了後、アクション項目と実行責任者と実行期限の三点がふくまれたアクションプランと呼ばれる表が作られました。
pp.140-141
まず最初に、通訳ガイド資格のための勉強の進捗を管理できる表を作成しました。これは、用紙一枚にそれぞれの参考書名を書き、その横に横書き棒グラフを作るのです。各参考書を消化した度合いに応じて塗りつぶしていくため棒グラフです。
そのとき注意してほしいのが、一つの棒グラフの縦幅は、参考書の量によって変化させるということです。
p.141
そうすることで、処理しなければならない全勉強量に対して、すでに終了した勉強量の比率が、色塗りされた部分の面積比でひと目で分かるのです。p.142
挫折しそうになったとき、今まで勉強してきた量の全てを捨ててしまうことが非常にもったいなく感じるのです。
p.144
自分の相性とぴったり合う本を一冊、購入してきます。そして、「へ〜」「なるほど〜」というような自分が感心した箇所や始めて知った新鮮な知識の部分などを、まずはマーカーで塗っていきます。そうすると、一冊がびっしりとマーカーで塗られます。これを基にして、そこから問題集を作っていくわけです。マーカーで塗られた部分の知識を問う問題を一つずつノートに書いていくのです。
Lifehack with Mac ストレスフリーの快適MACLIFEガイド [book]
Lifehack with Mac—ストレスフリーの快適MACLIFEガイド / こもり まさあき (著)

Chapter1 は Mac OS X や Safari の設定カスタマイズ、フリーフェアやシェアウェアの紹介など。
Chapter2 は Mail.app, Thunderbird や Flickr の使い方の説明。
Chapter3 は ウェブサービスの紹介。
Chapter4 も ウェブサービス (カレンダーやタスク管理) の紹介。
Chapter5 も マインドマップや情報共有に使えるソフトウェアやウェブサービスの紹介。
というわけで、タイトルにある「Lifehack」や「Mac」はあまり関係ない内容でした。
内容も、各ツールやウェブサービスの紹介レベルで、ハックにはなっていないと感じました。
ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する 絶対に失敗しないビジネス経営哲学 [book]
ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する 絶対に失敗しないビジネス経営哲学 / 島田 紳助 (著)
さまざまなサイドビジネスを成功させてきた島田紳介さんが考える商売のコツが解説されています。
お客さん、従業員、自分含め、みんなに幸せになってもらうことがポイント。
もちろん、サイドビジネスといえども「真剣」に取り組んできたから、成功できたのだと思います。
以下、読書メモ。
フリーエージェント社会の到来 「雇われない生き方」は何を変えるか [book]
フリーエージェント社会の到来 「雇われない生き方」は何を変えるか / ダニエル ピンク (著), Daniel H. Pink (原著), 池村 千秋 (翻訳), 玄田 有史

フリーエージェント社会の現状と未来の展望について、具体的な例を挙げならが説明してあります。
広い視野で、さまざまな事柄についてフリーエージェント社会を解説しているので、到来するフリーエージェント社会を眺望するのにお薦めです。
そこで、
一番面白いと感じたのは、これ。
これまで私たちは、仕事と家庭の境界線をはっきりさせなくてはならないと思い込んできた。しかし実は、仕事と家庭の境界線などというものは、毎日の通勤と同様、二十世紀になるまで必要とされていなかった。(p.223)
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉がはやっているが、そもそもバランスをとろうとするのではなく、「ブレンド」してしまうという考え方。
ただ、「ブレンド」するためには、フリーエージェント流のやり方をやっていかないと。
古いやり方は、月曜から金曜まで 5 日働いて、土曜と日曜は休むというものだった。これに対してフリーエージェント流は、月曜から日曜までの 7 日間に、仕事もするし、休みも取るのだ。(pp.135-136)
以下、読書メモ。
《続きを読む》
ウェブを変える10の破壊的トレンド [book]
2007 年のウェブのトレンドが豊富な例を挙げて説明されています (「破壊的」なトレンドかどうかは置いておいて)。
各章の最後に、その章で紹介したサービスとその URL のリストがあり、便利です。
が、索引として利用するには、どのページにそのサービスについての記述があるかというポインタが欲しかったです。
とにかく海外のウェブサービスが多く、網羅的に紹介されているので、知らなかったものについては順次試していきたいと思います。
知的生産の技術 [book]
「発見の手帳」という考え方とその書き方、それを使った知的生産法については非常に参考になりました。
読書法について。
著者は、本は隅から隅まで読むできで、斜め読みでは本当には理解できないという立場。
これには賛否両論あるかとおもいますが、2 つの視点で 2 重に読む、2 度読むといったあたりは、最近の読書本でも紹介されているやり方かと思います。
タイプライターの話など、古さを感じる部分もありますが、1969 年に出版されたにもかかわらず、現在にも通じる「知的生産」の考え方、やり方は、本質をとらえていると言ってよいでしょう。
p.216
くりかえしいうが、実行がかんじんである。実行しないで、頭で判断して、批判だけしていたのでは、なにごとも進展しない。どの技法も、やってみると、それぞれにかなりの努力が必要なことがわかるだろう。安直な秘けつはない。自分で努力しなければ、うまくゆくものではない。
というわけで、今日から少しずつでも実行。
以下、読書メモ。
《続きを読む》
2008 年 1 月に読んだ本 [book]
今月は 4 冊読みました。
* 日経 TRENDY (トレンディ) 2008年 02月号

ref.[2008-01-09-1]
* ウェブ時代をゆく いかに働き、いかに学ぶか / 梅田 望夫 (著)

ref.[2008-01-10-1]
* 投資信託にだまされるな! Q&A 投信の疑問・解決編 / 竹川 美奈子 (著)

ref.[2008-01-21-1]
佐藤可士和の超整理術 [book]
タイトルは「整理術」ですが、書かれているのは書類や PC のデータの整理の方法ではなく (それについても記述はあるが、) 思考をどのように整理し、物事の本質をとらえるかがメインのテーマだと感じました。
整理のノウハウの期待するのではなく、思考法の本として読むと楽しめると思います。
本書では、佐藤さんのこれまでのプロジェクトを例として多く取り上げています。
どのような思考法で彼の作品が生まれてきたのかが解説してあるので、彼の作品に共感を覚える人には分かりやすい例となっているのではないでしょうか。
以下、読書メモ
《続きを読む》
日経 TRENDY (トレンディ) 2008年 02月号 [book]
各証券会社、銀行がどの ATM と提携しているか、手数料は、といった内容が一覧でき分かりやすいです。
投資信託や、債権、ETF についても、同じように一覧でき、現在どこが一番手数料が安いのか、使い勝手がよいのかが分かりやすく書かれています。
外国債権や ETF の購入についても記述がある点が良かったです。
このような情報は自分で調べようとすると手間がかかるので 550 円というのはとてもお買い得だと思います。
2007 年 12 月に読んだ本 [book]
今月は 4 冊読みました。
* お金は銀行に預けるな 金融リテラシーの基本と実践 / 勝間 和代 (著)

ref.[2007-12-12-1]
* さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学 / 山田 真哉 (著)

ref.[2007-12-15-1]
* ひねり出す時間術 30分ジグザグ仕事術 / 清水 克彦 (著)

ref.[2007-12-17-1]
2日で人生が変わる「箱」の法則 / アービンジャー・インスティチュート (著), 門田 美鈴 (翻訳)

ref.[2007-12-21-1]